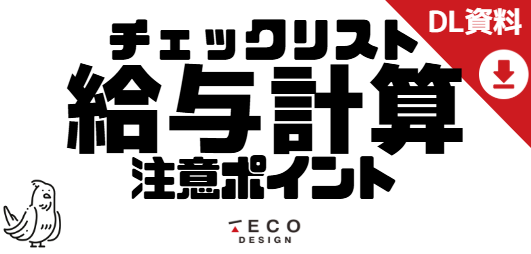【労務知識】3分で読める!師範の尊いお導き 入社一回目の給与計算を極めよ
本シリーズでは、CLOUD STATIONを運営するTECO Designの労務経験豊富なスペシャリスト「師範」による、労務業務についての解説をご紹介します!
労務初心者の方はもちろんのこと、部下や後輩を指導する立場の方、原点に立ち返りおさらいしたい方にもぜひご覧いだきたい内容です。
本記事のテーマは「入社一回目の給与計算を極めよ」です!
・・・
月末締め・翌月25日払いの企業において、1月1日に入社をした「月初入社の方」と1月16日に入社をした「途中入社の方」を想定した場合で、入社後初の給与(2月25日支給分)のチェックポイントをご紹介します!
今回は、マネーフォワードクラウド給与を使用しました。マネーフォワードクラウド勤怠との連携が完了していて、給与の自動計算がされている前提ですが、どういった点に注意すれば良いのでしょうか。
マネーフォワードクラウド勤怠のデータが連携されていると、一見すると給与計算に必要である情報は網羅されているように見えますが、「日割り計算」が必要な今回の状況では自動計算のままでは締めることができないので要注意です!
支給項目で注意したいポイント
欠勤日数を入力した際、基本的に欠勤控除は自動計算されますが※、月の途中入社の方は1月16日入社のため、「欠勤」扱いにしてしまっては実態と異なります。そもそも入社していないため、労働の義務のある出勤日に欠勤をしたわけではないからです。
このようなときには、会社にもよりますが、例えば月平均所定労働日数を分母にし、出勤日数を分子にして、日割り計算を手で行う必要が発生します。
※システムの支給項目の設定によります
また、通勤手当についても「出勤回数×一日の交通費(労働日)」と設定されていない場合には、同様に手動の日割り計算が必要になりますので要注意です。最初の月だけは定期券を買わずに、実費精算という場合などもあるでしょう。個々の会社によって違うと思います。
控除項目で注意したいポイント
次に、控除について見ていきましょう。
途中入社・月初入社の従業員の給与計算で一番気を付けたいのは、社会保険料(以下、社保)を、引くべきか否かです。社保については、基本的には入退社日をシステムに入力しておけば、基本的には良い状態になっているはずです。
社保の控除基準は、「末日に在籍しているかどうか」です。一部組合は保険料を先引きするところもありますが、社会保険は基本的に翌月徴収です。「末日に在籍していたかどうかによって、その月の社会保険料がかかるかどうか」「かかる場合翌月に徴収される」とお考えください。
今回例に挙げた月初入社(1/1)の方、途中入社(1/16)の方は、1月末日時点で在籍しています。そこで初めて「1月分の社保を控除すべき」という要件が発生しますので、2月支払いの給与では「1月分を控除する状態」になります。
またもう一点、40歳からの方が対象となる「介護保険」も要チェック!
こちらは、入社時の生年月日の情報を確認し、控除して良いのかどうかは目で確認するべきところです。ここで間違えてしまうと、何年間もその間違えた設定を踏襲してしまう可能性があります。
★社会保険料の金額ミスについてはこちらの動画でも「師範」による防止策をお話しています!
【師範の尊いお導き】社保のミスを防ぐために #2
雇用保険料は、事業の種別にもよりますが、「一般の事業(農林水産、清酒製造、建設以外)」の場合は総支給額に1000分の3を掛けた金額です。※2021年11月現在
途中入社の方の場合には、ここでも総支給額が正しい状態になっているか・日割り計算されているかを確認しましょう。
新入社員の給与計算 チェックポイント!
入社日によって、日割り計算があったり見るべきがポイントが異なったりします。
給与計算業務においては、入力よりもこれらの「チェック」がメインかと思います。
新入社員の給与計算においては、下記の項目が抑えておくべきポイントです。雇用契約書記載の手当があるのかどうか、日割りが必要かどうか、社保や雇用保険などの加入者であれば金額が正しいかどうか。また、所得税、住民税もポイントです。
- 金額マスタ
- 日割り計算が必要かどうか
- 加入保険ごとの控除の有無と金額
- 所得税:甲乙、扶養親族の数や本人ステータス(障害有無、寡婦/ひとり親 など)
- 住民税(あれば):金額と支払先はどこか
もう一歩踏み込んで確認するのであれば、加入保険ごとの控除有無を確認する際には、いくらの標準報酬等級で入社を手続きをしたのかもポイントです。
標準報酬に含めるものは、報酬全てです。残業手当が「固定」であれば標準報酬に入れる必要があります。他、毎月固定金額が支払われる金額は、標準報酬取得時の手続きで含んでおきましょう。
本記事でご紹介したように、クラウド給与計算で自動化できるところ、できないところがあります。自社でやりたいことはなにか?そのために必要な機能はなにか?そしてそれを満たすクラウドはどれか・・・など複数の観点と段階を踏み、サービス選定と運用設計を行うことをおすすめします。
本記事と同様の内容を、こちらの動画でもご紹介しています。ぜひ、併せてご覧ください!
カテゴリー
タグ
最近の投稿
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月