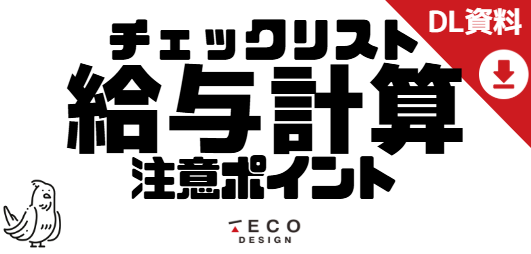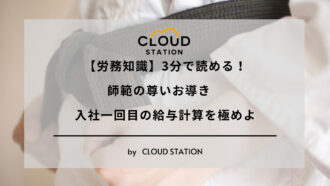所得税の源泉徴収金額をミスしたときの対処法

こんにちは。人事労務クラウドシステムを実際に体験して比較検討できるCLOUD STATION編集部です。
みなさんは、源泉徴収に関してどれくらいご存じでしょうか?
「会社員の人が給与をもらうときに差し引かれるあれでしょ?」というくらいしか知らない方も少なくないのではないでしょうか?
所得税とは、個人の一年間(1月1日〜12月31日)の所得に対してかかる税金です。税率は所得額によって異なる累進課税制をとっています。
その所得税を、会社側が毎月の給与や報酬からあらかじめ差し引くことを源泉徴収といいます。これは源泉徴収制度と言われ、原則全ての企業で義務化されています。
源泉徴収で差し引かれる税額は、あくまで所得額から決まった税率で割り出された暫定的な金額であるため、本来の税率とは異なる場合があります。
そこで、実際の年間給与所得から最終税額を確定させて精算するために行うのが年末調整です。
給与・賞与に対する源泉徴収税額の算出方法
源泉徴収の課税対象となるのは、社会保険料などを差し引いた給与所得です。それに加え、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている扶養家族などの情報と、「甲欄」をもとに源泉徴収税額を算出します。
扶養控除申告書が提出されなかった場合は「乙欄」が適用されて額が確定します。
※企業によっては「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を算出する方法」を用いている場合もあります。
また、給与所得以外では以下が源泉徴収の課税対象となります。
- 利子所得
- 配当所得
- 退職所得
- 報酬(原稿執筆料など) etc
基本的な所得税の算出方法については、ぜひ以下をご覧ください。
【給与計算の場合】
【賞与計算の場合】
源泉徴収税額の金額を間違えてしまった場合の対処法
「源泉徴収税額を間違えて算出し、徴収してしまった」という間違いは珍しくありません。
この場合の対処法は、対象の従業員が在籍しているか否かによって異なります。以下3つのパターンごとに解説します。
①対象の従業員が在籍している場合
その年の年末調整で従業員の最終税額が確定し、精算されます。 つまり、間違いが発覚した次の月から本来源泉徴収するべき金額を徴収すれば問題ありません。
ただし、この措置はあくまでも実務上の話であり、所得税追徴や加算税が発生する場合があります。
あくまで実務上の観点から考えられる対処法ですので、下記③の方法で精算する方が良いケースもあります。
②対象の従業員が離職していて別の会社で再就職している
転職先の会社での年末調整により従業員の最終税額が確定し、精算されます。
つまり、従業員の退職時に発行した源泉徴収票の訂正や再交付は基本的に必要ありません。
こちらもあくまで実務上の観点から考えられる対処法であるため、下記③の方法を検討することもおすすめします。
③対象の従業員が離職していて再就職していないor不明
対象者の年間の最終税額がどのように確定されるかは未定です。
そのため、まずは間違えて徴収してしまった月の本来の源泉徴収額を算出し、実際に徴収してしまった分との差額を本人口座に振り込み(もしくは徴収し)ましょう。その後、訂正された源泉徴収票を出し直すことが必要です。
※あくまで訂正可能な範囲は、本年支払分の給与のみです。
ただし、「自分で確定申告します」という本人からの申し出があった場合は、年間の最終税額が本人の確定申告で決定します。この場合、企業側で対応する実務は発生しません。
もしもに備えて正しい対応の理解を
源泉徴収額に限った話ではありませんが、会社(もしくは給与計算委託先など)が間違えて計算してしまった場合、従業員に知らせた上でしっかりと訂正することが誠実な対応と言えます。
クラウドシステムは手計算・表計算ソフトよりもヒューマンエラーを防ぎやすいという特徴はありますが、発生率を0に抑えることはできません。
もしものことが起こった場合の対処法も理解した上で、実務を進めていきましょう!
カテゴリー
タグ
最近の投稿
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月